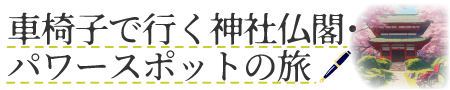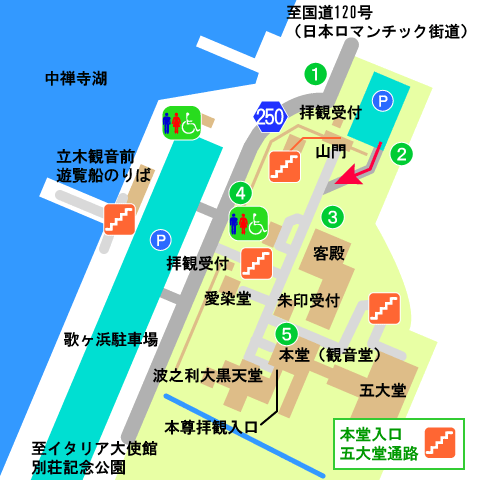中禅寺は、栃木県日光市の中禅寺湖畔に建つ天台宗の寺院で、日光山輪王寺の別院です。御本尊の十一面観音は、日光山を開いた勝道上人が根の生えたままの立木に彫刻したと伝えられるところから、「立木観音」の名で呼ばれています。
旅行先の地図
旅行先の概要
| 御本尊 | 十一面千手観音菩薩 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市中禅寺歌ケ浜2578 |
| 交通 |
中禅寺温泉から東武バス(中禅寺スカイライン半月山行)経由で約3分、「立木観音前」下車【季節運行につき注意】。 日光宇都宮道路「清滝IC」から車で約30分。 |
| 拝観料 | 大人500円、小中学生200円【身障者は大人100円、小中学生無料】 |
| 駐車場 | 山門前に舗装済の無料駐車場あり。他にも県道沿いに舗装済の歌ヶ浜駐車場【身障者用区画あり】(無料)あり。 |
| URL | http://rinnoji.or.jp/precincts/cyuuzenji |
| 連絡先 | 中禅寺・立木観音 0288-55-0013 |
歴史・由来
中禅寺は、栃木県日光市の中禅寺湖畔に建つ天台宗の寺院で、日光山輪王寺の別院です。坂東三十三観音霊場の第18番札所にも位置づけられています。
寺伝によれば、延暦3年(784)に日光山を開いた勝道上人が日光二荒山神社の神宮寺として建立したのが始まりとされます。明治の神仏分離で日光二荒山神社中宮祠から分離されて日光山輪王寺の別院となり、明治35年(1902)には山津波により中宮祠近くにあった堂宇が流されたため、中禅寺湖畔の歌ヶ浜にある現在地に再建されました。
本堂(観音堂)に安置されている御本尊の十一面観音は、カツラ材の一木造に42本の腕の部分を別材で拵えた像高6メートルの大きな像で、国の重要文化財に指定されています。この仏像は勝道上人が根の生えたままの立木に彫刻したと伝えられるところから、「立木観音」の名で呼ばれています。
本堂脇の「波之利(はしり)大黒天堂」は、勝道上人が日光山開山の折に中禅寺湖の波の上に現れて男体山登山を助けたという大黒天を祀り、安産や足止め(家出人の帰還や浮気防止)の御利益があるとされています。
また、本堂前の「愛染堂」には愛染明王像が祀られ、傍らにカツラの木がありますが、ここは往年の映画『愛染かつら』のロケ地として有名となったことから(なお、原作は長野県上田市の北向観音がモデル)、縁結びの御利益で信仰を集めています。
さらに、本堂後背の崖の上に建つ「五大堂」は、勝道上人開山1200年記念事業として昭和44年(1969)に完成を見たもので、もと日光東照宮の護摩堂に安置されていた降三世明王、軍茶利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王、不動明王の五大明王を祀っています。車椅子不可ですが、ここからは優美な中禅寺湖の風景が一望できます。
例年8月4日には、中禅寺執行(しぎょう)が勝道上人の墓のひとつとされる中禅寺湖内唯一の島・上野島(こうずけしま)ほかを船で巡拝する「船禅頂」という行事があり、これは勝道上人が湖畔の霊場を船で巡拝したことが発祥とされています。
車椅子で旅行するポイント
周辺の名所・観光スポット
華厳の滝
和歌山県の那智の滝、茨城県の袋田の滝とともに「日本三大名瀑」の一つとされる奥日光の名瀑。高さ97メートルの断崖を中禅寺湖の湖水が豪快に流れ落ち、滝壺にイワツバメが舞う。明治36年(1903)に旧制一高生の藤村操が「巌頭之感」を遺して投身自殺をして有名となったが、現在では防止柵が設置されている。
【エレベーターで展望台まで車椅子可】
■参考リンク:華厳滝エレベーター
日光自然博物館
奥日光の動植物のなどを紹介する自然系展示室、古代の日光開山から国際避暑地としてにぎわった近代史までを解説する人文系展示室をはじめ、奥日光の自然や観光の情報発信拠点として整備された施設。関係施設として中禅寺湖畔にイタリア大使館別荘記念公園がある。
【身障者用トイレ、スロープ、車椅子貸出あり】
■参考リンク:日光自然博物館
奥日光湯元温泉
日光山を開いた勝道上人が延暦7年(788)に発見したとされる古湯で、背後の温泉ガ岳に薬師如来を祀ったと伝えられる。泉質は硫化水素泉で、神経痛、冷え症、糖尿病などに効くとされる。湯ノ平に源泉があり、温泉が湧き出る様子を見ることができる。
【バリアフリー対応の宿泊施設あり】
■参考リンク:奥日光湯元温泉旅館協同組合