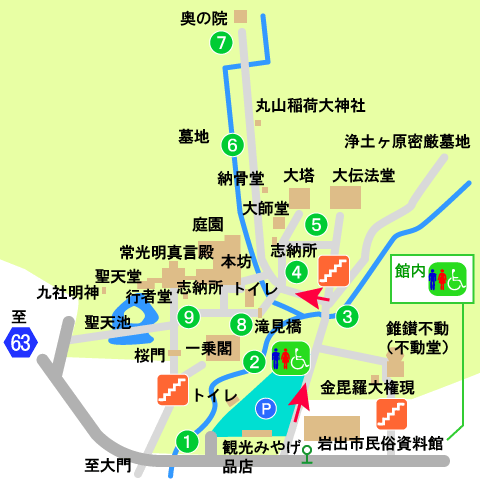根来寺(ねごろじ)は、和歌山県岩出市にある覚鑁開山の寺院で、中世には根来衆とよばれる僧兵1万人を擁する一大宗教都市が築かれましたが、豊臣秀吉の焼き討ちに遭い没落しました。境内の「大塔」と称する国内最大の多宝塔は国宝に指定されています。現在は新義真言宗の総本山となっています。
旅行先の地図
旅行先の概要
| 御本尊 | 大日如来 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県岩出市根来2286 |
| 交通 |
JR阪和線「和泉砂川駅」から南海ウイングバス(岩出樽井線「岩出駅前」行き)経由で約10分、「根来寺」停留所下車 「根来寺」下車 阪和自動車道「泉南IC」から車で約20分 |
| 拝観料 | 境内無料 ただし、大塔・大師堂・大伝法堂・名勝庭園(共通)は拝観料として大人(中学生以上)500円、小人無料【障害者手帳保持者は無料】 |
| 駐車場 | 境内入口に砕石敷の無料駐車場あり |
| URL | 根来寺 |
| 連絡先 | 根来寺寺務所 0736-62-1144 |
歴史・由来
和歌山県岩出市にある新義真言宗の総本山とされる寺院です。
平安時代後期の大治5年(1130)、空海以来の才とうたわれた覚鑁(かくばん)が高野山内に開いた大伝法院が始まりとされます。
覚鑁は大伝法院の座主として堕落した高野山の状況を改めようとしますが、刺客に狙われた上に高野山を追放され、当時大伝法院の荘園の一つであった根来の地に落ち延びました。この事件の直前、覚鑁は3年あまりに及ぶ無言の行を修したのち、『密厳院発露懺悔文』という宗教家としての自戒の文章を認めています。
この根来寺は、中世の最盛期には寺領50石ないし70石を有し、根来衆とよばれる僧兵(行人)1万人を抱える一大宗教都市を形成しており、僧衆による鉄砲隊も組織されて、本願寺との石山合戦の際には織田信長に味方するなどして活躍しています。
しかしながら、近隣の雑賀衆とともに羽柴秀吉とは敵対したため、天正13年(1585)にはその焼き討ちに遭って(または自焼)堂宇のほとんどを失いましたが、江戸時代には徳川家康の寄進や紀伊徳川家による堂宇の再興がありました。
境内には「大塔」と通称される、文明12年(1480)ごろから建築が始まったとみられる高さ40メートルの日本最大の多宝塔があり、国宝に指定されています。
車椅子で旅行するポイント
移動のしやすさ ★★★★☆
バリアフリーの状況 根来寺の境内には一部段差のある箇所や坂があるものの、舗装されている参道が割と多く、介助があれば車椅子での参拝も可能となっている。根来寺境内入口の駐車場奥及び岩出市民俗資料館内に身障者用トイレがある。ただし、堂内の拝観は車椅子のままでは難しい。
周辺の名所・観光スポット
岩出市民俗資料館
根来寺入口にある岩出市の展示施設。常設展示では「岩出市の風土と暮らしの移り変わり」をメインテーマとして、岩出の自然環境と歴史・文化について紹介している。学術調査により根来寺周辺から出土した遺物も多数展示されているほか、企画展や根来塗講座なども行っている。
【身障者用トイレ、スロープ、駐車場(2台)、車椅子貸出あり】
■参考リンク:岩出市>岩出市民俗資料館
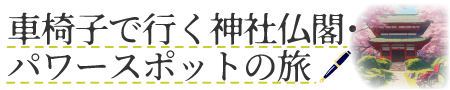

 東京周辺 神社仏閣どうぶつ案内 神使・眷属・ゆかりのいきものを巡る
東京周辺 神社仏閣どうぶつ案内 神使・眷属・ゆかりのいきものを巡る