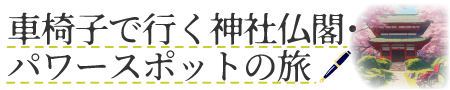「車椅子で行く神社仏閣・パワースポットの旅」で紹介されている全国各地の寺院の記事の一覧です。
 寺院
寺院 善楽寺
善楽寺は、高知県高知市にある真言宗の寺院で、四国八十八か所霊場の第30番札所にあたります。大同5年(810)、弘法大師空...
 寺院
寺院 本土寺
本土寺は、千葉県松戸市にある日蓮宗の寺院です。建治3年(1277)、源氏の名門である平賀忠晴の屋敷跡に、日蓮の弟子にあた...
 寺院
寺院 高幡不動尊
高幡不動尊は、東京都日野市にある真言宗智山派別格本山の寺院で、正しくは「高幡山明王院金剛寺」といいます。平安時代初期、慈...
 寺院
寺院 四天王寺
四天王寺は、大阪府大阪市にある和宗の総本山で、救世観音を本尊としています。推古天皇元年(538)に聖徳太子が開基した歴史...
 寺院
寺院 観音寺
観音寺は、香川県観音寺市にある真言宗の寺院で、四国八十八箇所霊場の第69番札所にあたります。同じ境内には第68番札所の神...
 寺院
寺院 尾道浄土寺
浄土寺は、広島県尾道市にある真言宗泉涌寺派の大本山です。推古天皇の時代に聖徳太子が開創したと伝えられ、嘉暦元年(1326...
 寺院
寺院 井波別院瑞泉寺
井波別院瑞泉寺は、富山県南砺市にある浄土真宗大谷派の寺院です。明徳元年(1390)に本願寺5世綽如上人によって開かれたも...
 寺院
寺院 城端別院善徳寺
城端別院善徳寺は、富山県南砺市にある浄土真宗大谷派の寺院です。室町時代に蓮如上人が開基し、戦国時代に城端城主が現在地に誘...
 寺院
寺院 丹波白毫寺
白毫寺は、兵庫県丹波市にある天台宗の寺院で、慶雲2年(705)に法道仙人が開山したと伝わります。花房の長い「九尺藤」と呼...
 寺院
寺院 弘前長勝寺
長勝寺は、青森県弘前市にある曹洞宗の寺院です。享禄元年(1528)、津軽氏の祖である大浦光信の菩提を弔うため創建されたも...